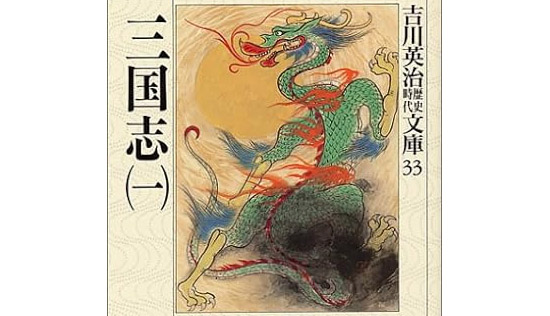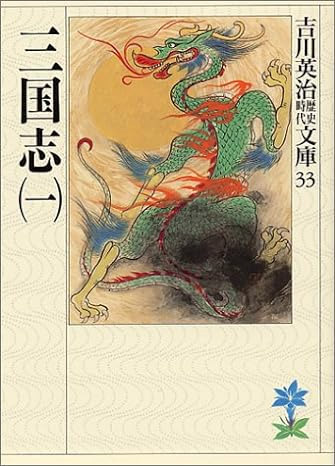
三国志(一)
著者:吉川英治
作品紹介・あらすじ
一話を3分で読む三国志。誰でも読みやすく紹介していきます。
桃園の巻
黄巾賊
一
後漢の建寧元年(168年) 現在2023年なので、今から1855年前のこと。
涼秋の8月。
黄河のほとりに、一人の旅人がいた。
身なりは見すぼらしいが、腰に剣を差し、眉は秀で、聡明そうな瞳。
つねにどこかに微笑をふくみ、総じて賤しげな容子はない。
年の頃は24、5。
幾千万年もこうして流れているのかと思われる黄河の水を飽きずに眺めていた。
どうしてこの河の水は、こんなに黄色いのか?
よくよく見ると、水そのものが黄色いのではない。
黄色い砂の粒が水に混じって一面におどっているため、黄色く濁って見えるのであった。
「ああ……、この土も」
彼は、大地の土を一掴み手に取り、はるか西北の空へ投げ放った。
支那の大地を作ったのも、黄河の水を黄色くしたのも、みなこの砂の微粒である。
そしてこの砂は中央アジアの砂漠から吹いてきた物である。
何万年も前の大昔から、吹き送られ積り積った大地である。
「わたしの先祖も、この河を下って…」
彼は自分の体に今、脈打っている血液がどこからきたか
遠い根元までを想像していた。
支那を拓いた漢民族も、その砂の来る中央アジアの山岳を越えてきた。
黄河の流れに添いつつ、農業を拓き、産業を興し、何千年の文化を培ってきた。
「ご先祖様、見ていて下さい。いやこの劉備を鞭打って下さい。劉備はきっと漢の民を興します。漢民族の血と平和を守ります。」
劉備青年は、黄土と黄河の流れに誓った。
(2023.10.6)
二
急に背後から「黄巾賊の仲間だろう?」と大声がした。
振り向くと県の役人がおり、
一人は鉄弓を持ち、もう一人は半月槍をかかえていた。
「私は、涿県楼桑村の者で蓆を織ったり簾をつくって売っています。」
と劉備は答えた。
だが劉備の腰に下げている煌びやか剣を見ると
「盗んだものだろう」と詰め寄ってきた。
「これは父の形見で盗んだものではありません。」
と素直ではあるが、凛とした答えである。
役人は劉備の眼を見ると、急に眼をそらして
「ではなぜ半日もここに座り込んで何をしているのか?
昨晩も近村で黄巾賊が暴れたところだ。怪しまれても仕方があるまい。」
「洛陽船を待っております。
母親の好物の茶を買って帰ろうと思っているのです。」
「茶を」役人は眼をみはった。
茶というものは、高価で貴重なものであり、
瀕死の病人に与えるか、高貴な人でないと飲めないものだった。
陽が傾きかけたころ
旗を掲げた洛陽船が上流に見えてきた。
劉備はやっと草むらから立ち上がった。
(2023.10.10)
三
洛陽船は客船や貨船と違い、一目でそれとわかる。
無数の紅い龍舌旗をひるがえし、船楼は五彩に塗ってあった。
「おーい」
劉備は手を振った。
船は劉備には見向きもせず
帆をおろしながら、下流の水辺の村に停泊した。
洛陽船を待っていたのは、劉備だけではない。
ロバを引いた仲買人の群れ、糸や綿を積んだ百姓
獣肉や果物を籠に入れて待つ物売り、などなど
そこにはすでに市が立とうとしていた。
黄河の上流、洛陽の都は、後漢の第12代帝王、霊帝の居城がある。
珍しい物産や文化の粋はほとんどそこで作られ、全支那へいきわたる。
幾月かに一度、文明の製品を積んだ洛陽船は、
黄河沿岸の町、村、部落など市の立つところに船を寄せて交易した。
劉備がまごついている中、慌ただしい取引は、瞬く間に終わり
仲買人も百姓も物売りも、夕やみの中に消えていった。
劉備は、船の商人らしき男を見かけて、あわててそばに寄って聞いた。
「茶を売ってください。茶が欲しいんです。」
洛陽の商人は振り向いて言った。
「え、茶だって?
あいにくお前さんに分けてやるような安茶はない。
一葉いくらというような高級品しか船には積んでいない。」
「結構です。たくさんは要りませんが。」
「おまえは茶を飲んだことがあるのか?
地方の衆が葉を煮て飲んでいるのは、あれは茶ではないよ。」
「はい、その本当の茶を分けていただきたいのです。」
劉備は懸命にいった。
茶がいかに高価で貴重か、彼の身分でそれを求めることの無謀さもよく知っていた。
劉備の懸命な面持ちと、真面目に欲する訳を話す態度を見ると
洛陽の商人もやや心を動かされ
「では少し分けてあげてもよい。だが、その代価はお持ちかね?」
と聞いた。
(2023.10.11)
四
「持っております。」
劉備は、懐から銀や砂金を惜しげもなくだした。
洛陽の商人は、目方を計りながら
「これでは、よい茶はいくらも上げられない。」
「何ほどでもよいです。
母が眼を細めて、よろこぶ顔が見たいので。」
「そんなに欲しいのか。
これだけの銀を貯めるのには大変だったろう。」
「二年かかりました。自分の食べたい物や着る物も、節約して。」
「そう言われると断れないな。
おまえさんの孝行心に免じて、茶を分けてやろう。」
やがて船室の中から、錫の小さな壺を一つ持ってきて、劉備に与えた。
「ありがとうございました。」
劉備は、茶壺を持って、岸を離れてゆく船を拝んでいた。
もう瞼には、母の喜ぶ顔がちらちらする。
しかし、故郷の涿県楼桑村までは百里もあった。
彼は村の宿へ泊ることにした。
すると夜半頃、宿の亭主が慌ただしく起こしにきた。
眼をさますと戸外は真っ赤で、パチパチと火の燃える音がする。
「洛陽船と交易した仲買人たちを狙って、黄巾賊がやってきたのですよ。」
外へ出てみると、近所は焼け、家畜は異様なうめき声を放ち、
女子供は、炎の下に悲鳴をあげて逃げまどっていた。
見れば、夜叉のような人影が、矛や槍や鉄杖をふるって、
逃げ散る人々を手当たり次第に殺戮している。
それらの悪鬼は皆、髪のうしろに黄色の巾をかけてた。
黄巾賊の名は、そこから起こったものである。
本来は支那の尊い色であるはずの黄土の国色も、
善良な民を震え上がらせる悪鬼の象徴となっていた。
(2023.10.12)
五
劉備は、剣に手をかけ、家の扉を蹴って今にも躍りだそうとした。
しかし、一人で百人の賊を斬ったところで天下は救われない。
彼は思い直し、焼き払われた水村を後にした。
途中、樹木の影に古い孔子廟があった。
劉備は、廟にひざまずき
「孔子は文を以て、世に立ったが
わたしは武を以て黄魔鬼畜を打ち、民を救い平和な世の中にしてみせよう」
と誓った。
すると廟の中で
「わははは」と大声で笑った者がいた。
二人の大男が突然、廟から飛び出してきて、
劉備は襟首を抑えつけられてしまった。
(2023.10.13)
六
「悪いものに出くわした。」
と劉備は思った。
明らかに黄巾賊の仲間である。
それも頭分の者であることは面構えや服装ですぐにわかった。
黄巾賊は、総大将の張角とその2人の弟は特に
大賢良師 張角
天公将軍 張梁
地公将軍 張宝
と呼ばれ、その下に、黄巾賊の武将を指す
大方、中方、小方で組織されていた。
劉備の前に腰かけているのは、馬元義という大方であった。
「黄魔鬼畜とは何のことか?」という馬元義の問いに
劉備は答えをはぐらかした。
「逃げるようなら即刻叩き切ってやるまで」と脅され
劉備は渋々、荷物を持たされ、北の町を目指しお供することになった。
(2023.10.16)
流行る童歌
一
驢(ロバ)にのる馬元義と半月槍をかつぐ手下の甘洪の間に挟まれながら
劉備は、賊の荷物を背負って黙々と歩き続けた。
丘陵と河と平原ばかりの道を、四日も歩きつづけた。
「おう、甘洪。飯が食えるぞ。冷たい水にもありつけるぞ。
見ろ、むこうに寺がある。」
一叢の木立と沼があった。沼には紅白の蓮の花がいっぱいに咲いていた。
そこの石橋を渡り、荒れ果てた寺門の前で、馬元義は驢を降りた。
門扉には黄巾賊の黄色の紙が貼ってあった。
「この寺も黄巾の仲間に入っている奴ですぜ」
「おうい、誰かいねえのか」
甘洪は薄暗い堂の中を、怒鳴りながら覗いてみた。
何もない堂の真ん中に、骨と皮ばかりの老僧がいた。
しかし、老僧は眠っているのか、死んでいるのか、
虚ろな眼を向けたまま、答えもしない。
(2023.10.17)
二
甘洪は、半月槍の柄で、老僧の脛をなぐった。
老僧は、やっと眼を開けて、眼前の甘と馬と劉青年を見まわした。
「食べ物があるだろう。早く支度をしろ」甘がいう。
「・・・ない」
老僧は、蝋のような青い顔を、力なく振った。
「ない?――これだけの寺に食べ物がないはずはねえ。
家探しして、もし食べ物があったら、その首をはね落とすぞ」
「どうぞ!」老僧は、うなずいた。
そして、枯れ枝のような肘を上げ、後ろの祭壇や壁や四方をいちいち指して
「ない! ない! ない! 仏像さえない! ひとかけらの食べ物もここにはない!」
と泣くような声でいった。
「みんな、黄巾をつけたお前たちの仲間が持っていってしまった。
イナゴの群れが通ったあとの田みたいだよここは……」
「じゃあ、冷たい水でも汲んでこい」
「井戸には毒が投げ込んである。飲めば死ぬ。
これもお前たちの仲間が、残党が隠れぬようにと、毒を投げ入れていったのだ。」
「ならば、泉があるだろう。あんな綺麗な蓮の花が咲いている池があるのだから、
冷水が湧いているにちがいない」
「なにぞ蓮の花が美しいものか。
蓮の根元には、お前たちの仲間に殺された善良な農民や女子供の腐乱した死骸でいっぱいだよ。」
馬元義たちは、しかたなく、寺を出ていこうとした。
すると、その時はじめて、賊の供をしている劉青年の存在に気付いた老僧は、
穴のあくほど、劉青年の顔を見つけていたが、突然
「あっ?」
と、打たれたような驚きの声を発して、立ち上がった。
(2023.10.18)
三
老僧は、劉備の面をまじまじと見据え、まばたきもしなかった。
やがて
「あ、あ! あなただっ
あなたこそ、暗黒の国に楽土を作り、乱麻の世に道を示し、
塗炭の底から民を救ってくれるお方にちがいない」といった。
「とんでもない。私は涿県の貧しい蓆売りです。」
「いいや、あなたの人相に現れておる。
祖先は帝系の流れか王侯の血を引いていたろう」
「父も祖父も楼桑村の百姓でした」
劉備は首を振った。
「もっと先は……」
「わかりません」
「わからないなら、わしの言を信じよ。」
堂の外へ先に出たが、劉備がなかなか出てこないので、馬元義はしびれをきらして
「やいっ劉、荷物を持って早くこい」と、どなった。
「劉、今聞いていると、てめえは行く末、偉い者になる人相を備えているそうだな。
俺も実は、てめえは見込みのある野郎だと見ているんだ。
どうだ、俺の部下になって、黄巾党の仲間にならないか」
「はい、有難うございます。
しかし、私には、故郷に一人の母がいます。私が旅に出ている間も、痩せるほど子の心配ばかりしているものですので、折角ですが、お仲間には入れません」
「そりゃ貧乏ばかりさせておくからだ。
黄巾党に入って、腹をふくらせておけば、子の心配などしているものか」
(2023.10.19)
四
馬元義は、黄巾党の起こりを説きだした。
今から10年ほど前、河北省に、稀世の秀才と郷土でいわれた、張角という無名の士がいた。
張角はある時、山中で、異相の道士に出会った。
道士の名は、南華老仙といった。
この翁は、張角に、太平要術という三巻の書物を授け、
「天下の塗炭を救い、道を興し、善を施すがよい。
もし悪心を起こす時は、天罰がくだり、たちどころに身を亡ぼすであろう」
といい、一颯の白雲となって飛び去ってしまった。
張角は、そのことを、山を降りてから、里の人々に自ら話した。
里の人々は、「郷土の秀才に神仙が宿った」と真にうけて
張角を救世の方師と崇めて、触れまわった。
ある年、悪疫が流行して、村にも毎日おびただしい死人が出た。
張角は、今、神が我をして、出でよと命じ給う日であると
草門を開き、病人を救いに出たが、その時もう、彼の門前には、500人の者が、弟子にしてくれと、ぬかづいていたという。
500人の弟子は、彼の命に依って、
金仙丹、銀仙丹、赤神丹の秘薬をだすさえ、悪疫の地をみて廻った。
秘薬をもらった民は、皆、数日で治った。
それでも治らぬ者は、張角自身が祈祷を行うと、たちどころに治ったという。
張角の周りには、たくさんの人々が集まってきた。
たちまち、彼の勢力は、諸州にひろまった。
張角は、その弟子たちを、36の方を立たせ、階級を作り、大小に分かち、優秀なものには、軍帥や方帥の称号を授けた。
また、張角の兄弟、張梁、張宝を天公将軍、地公将軍と呼ばせ、最大の権威をにぎらせ
自身はその上に君臨し、大賢良師張角と称していた。
これがそもそもの、黄巾党の起こりだとある。
初め張角が、常に、結髪を黄色い巾でつつんでいたので、それが全軍に広まり
いつか党員の徽章となったものである。
(2023.10.20)
五
黄巾党は、黄色い軍旗に
「蒼天已死
黄夫当立
歳在甲子
天下大吉」
という宣文を書き、童謡風にやさしい作曲をつけて、唄い流行らせた。
唄った後は、張角の名を囃して、
今にも天上の楽園が地上に実現するような感じを民衆に抱かせた。
しか、黄巾党が跋扈すればするほど、楽土はおろか、一日の安穏も訪れなかった。
張角は、服従する愚民どもには、
「太平を楽しみ、我が世を謳歌せよ」と
暗に逸楽と略奪を奨励した。
そのかわり、逆らう者は、容赦なく殺し、財宝を掠めとることが日課だった。
中央の洛陽の王城に、このことを知らせる事、頻繁だったが
漢帝の宮中は、退廃と内乱で地方へ兵をやるどころではなかった。
後漢を興した光武帝から二百余年、桓帝が逝いて、十二代の霊帝はまだ十二、三歳の幼少であり、補佐役の重臣は、幼帝を欺き合い、真実のある人材は、みな野に追わせてしまうという状態であった。
ある年。
幼帝が温徳殿に出御なされると、にわかに、狂風が吹いて、長さ二丈(約六メートル)余りもある青蛇が、帝のそばに落ちてきた。
射止めようとしたが、突如大風が吹き荒れ、青蛇は雲となって飛び去り、その日から三日三晩、大雨が降り続き、洛陽の民家の浸水2万戸、崩壊したもの1千戸、溺死者怪我人数え切れないという大災害が生じた。
また、赤色の彗星が現れたり、五原山の山津波に部落数十が、一夜にして埋没したり、凶兆ばかり起こった。
(2023.10.22)
六
そんな凶兆のあるたびに、
「蒼天スデニ死ス」の歌は、盲目的にうたわれて行き、賊党に加担して、略奪、横行、殺戮をする者が、ふえるばかりだった。
黄巾賊の勢力は、今では青州、幽州、徐州、冀州、荊州、揚州、兗州、余州等の諸地域に及んでいた。
馬元義は、長々と、そうした現状や、黄巾党の勃興などを、自慢そうに語った。
「劉、今に天下は黄巾党のものになる。後漢は滅び、次の新しい代になる」
「では、張角良師は、後漢を亡ぼした後、自分が帝位につく肚なんですか」
劉備は、訊ねた。
「それはいえない。劉備、てめえが俺の部下になると約束するなら聴かせてやろう」
「なりましょう」
「では打ち明けてやるが、帝王の問題は重大な評議になる。匈奴(蒙古族)とも相談しなければならいからな」
「へえ?なぜです。我々漢民族を脅かしてきた異国の匈奴などと相談する必要があるのですか」
「それは大いにあるさ」と、馬は当然のように
「いくら俺たちが暴れ廻ろうたって、背後から、軍費や兵器をどしどし廻してくれる黒幕がなくっちゃ、こんな短い年月に、後漢の天下を攪乱することはできなないじゃねえか」
「えっ、では黄巾賊のうしろには、匈奴がついているわけですか」
「そうだ、だから俺たちは絶対に負けるはずはないさ。
どうだ劉、俺が勧めるのは、貴様の出世のためだ。部下になれ、すぐここで、黄巾賊に加盟せぬか」
「結構なお話です。母も聞いたら喜びましょう。けれど、親子の中にも礼儀ですから、一応、母にも告げた上でご返事を……」
言いかけている時、馬元義は不意に起き上がって
「やっ、来たな」と、彼方の平原を向かって、眉に手をかざした。
(2023.10.23)
白芙蓉(びゃくふよう)
一
それは五十名ほどの賊の小隊であった。
「やあ、李朱氾。遅かったじゃないか。
ゆうべの収穫はどうだった。洛陽船を的にだいぶ諸方の商人が泊っていた筈だが」
「大していう程の収穫もなかったが、一村焼き払っただけの物はあったよ。
だが、一人惜しいやつを取り逃がした」
「惜しい奴?それは何か高価な財宝でも持っていたのか」
「なあに、砂金や宝石じゃないが、洛陽船から、茶を交易した男があるんだ。
知っての通り、茶ときては、張角様の大好物。
その男が泊った旅籠も目星をつけておき、その近所から焼き払って踏み込んだところ、いつの間にか、逃げ失せてしまって、とうとう見つからない」
劉備は、驚いた。そして思わず、懐中に隠していた錫の茶壺をそっと触ってみた。
すると、馬元義は、劉青年を振り向いてから、李に向かって
「それは、幾つくらいの男か」
「そうさな。部下の話によると、まだ若いみすぼらしい風態の男だが、どこか凛然としているから、油断のならない人間かもしれないといっていたが」
「じゃあ、この男ではないか」
馬元義は、すぐ傍らにいる劉備を指さして、いった。
李は、部下の丁峰を呼んで、確認させた。
「この男です。この若い男に違いありません」
「よし」
李は、そういうと、馬元義とともに、いきなり劉備の両手を左右からねじあげた。
(2023.10.24)
二
「こら、貴様は茶をかくしているというじゃないか。その茶壺をこれへ出してしまえ」
劉備は、観念した。しかし、故郷の母が、いかにそれを楽しみに待っているかを思うと、自分の生命を求められたより辛かった。
劉備は、懐中の茶壺は出さす、腰に佩いている剣の帯革を解いて
「これこそは、父の遺物ですから、自分の生命の次の物ですが、これを献上します。ですから、茶だけは見逃してください」と懇願した。
すると、馬元義は、
「おう、その剣は、俺がさっきから眼をつけていたのだ。貰っておいてやる」
と取り上げて「茶のことは、俺は知らん」と、うそぶいた。
李朱氾は、前にもまして怒り出して、一方へ剣を渡して、俺にはなぜ茶壺を渡さないかと責めた。
劉備は、やむなく、肌深く持っていた錫の小壺まで出してしまった。
賊の小隊はすぐ先へ出発する予定らしかったが、ひとり物見が来て、ここから十里ほどの先の河べりに、県の吏軍が約五百ほど夜陣を張り、われわれを捜索しているらしいという報告をもたらした。
で、にわかに「では、今夜はここへ泊れ」となって、約五十の黄巾賊は、そのまま寺を宿舎にして、携帯の食料を解きはじめた。
夕方の炊事の混雑をうかがって、劉備は今こそ逃げるによい機と、薄暮の門を、そっと外へ踏み出しかけた。
「おい、どこへ行く」
賊の哨兵は、見つけるとたちまち、大勢にして彼を包囲し、奥にいる馬元義と李朱氾へすぐ知らせた。
(2023.10.26)
三
劉備は、捉えられ、牢に入れられてしまった。
「やい、劉。お前は、官の密偵だろう。今夜、十里ほど先まで県軍が来て、野陣を張っているそうだから、それに連絡を取るために、抜け出そうとしたのだろう」
馬元義と李朱氾は、かわるがわるに来て、彼を拷問した。
劉は一口も物をいわなかった。こうなったらからには、天命にまかせようと観念しているふうだった。
「こりゃひと筋縄では口をあかんぞ」
李は、馬へ向かってこう提議した。
「俺は、明日の早朝、張角良師の総督府へ参り、例の茶壺を献上するつもりだが
こいつも引っ立てて行って、軍法会議にさし廻してみようと思う。
思いがけない拾い物になるかもしれぬぜ」
よろかうと、馬も同意した。
斎堂の扉は、かたく閉められ、夜が更けると、ただ一つの高い窓から、銀河の秋天が冴えて見える。
劉備は、生き恥をさらして殺されるより、いっそ、ひと思いに死なんか と考えた。
すると彼の前に一筋の縄が下がってきた。
縄の端には短剣が結いつけてある。
(2023.10.27)
四
彼は、短剣で、自身の縄目を切った。
そして縄につかまり、石壁をよじ登り、窓から外を見た。
そこには、骨と皮ばかりの先程の老僧が、こちらを手まねきしていた。
老僧は、彼を抱きかかえるようにして、物もいわず駆け出した。
「老僧、いったりどちらに逃げるんですか」
「まだ、逃げるんじゃない。あの塔まで行ってもらうのじゃよ」
見ると、疎林の奥に、高く聳える古い塔があった。
老僧は、あわただしく古塔の扉をひらいて中へ隠れた。
暫く待っていると、白馬とひとりの美人を、連れて出てきた。
「こちらは地方県城を預かっておられた、領主のお嬢さまじゃ
黄巾賊の乱入にあって、県城は焼かれ、ご領主は殺され、家来は四散した
ここから十里ほどの河べりに陣している県軍の隊まで、届けてくれはしまいか」
(2023.10.28)
五
老僧はなお、語り続けた。
県の城長の娘は、名を芙蓉といい姓は鴻ということ。
また、今夜近くの河畔にきて宿陣している県軍は、きっと先に四散した城長の家臣が、残兵を集めて、黄巾賊へ報復を計っているに違いないということ。
だから、芙蓉の身を、そこまで届けてくれさえすれば、後は以前の家来たちが守護してくれる、というのだった。
「承知しました。けれど和上、あなたはどうしますか」
「案ずることはない。鴻家の阿嬢を助けて上げたいという、心だけで生きていたが、今は、そのことも、頼む者に頼み果てたし、あなたという者をこの世に見出したので、思い残りは少しもない」
老僧はそう言い終わると、風のごとく、塔の中へ影をかくした。
「和上さま。和上さま!」
芙蓉は慈父を失ったように、扉をたたいて泣いていたが、その時、高い塔の頂で、再び老僧の声がした。
「青年。わしの指さすほうをご覧。――ここの疎林から西北だよ。北斗星がかがやいておる。それを的にどこまでも逃げてゆくがよい。南も東も蓮池の畔も、寺の近くにも、賊兵の影が道をふさいでいる。逃げる道は、西北しかない。それも今のうちじゃ。はやく白馬に鞭打たんか」
劉備は、彼女の細腰を抱き上げて、白馬の鞍にすがらせた。
「ご免」といいながら、劉備ものって一つ鞍へまたがった。そして片手に彼女をささえ、片手に白馬の手綱をとって、老僧の指さした方角へ馬首を向けた。
塔上の老僧は、それを見おろすと、わが事おわれり――と塔上の石欄から百尺下の大地へ、身を躍らして、五体の骨を自分でくだいてしまった。
(2023.11.1)
張飛卒
一
白馬は疎林の細道を西北へ向ってまっしぐらに駆けて行った。
「オ。あれへ行くのは、劉備だ。女も逃がすな」
疎林の陰を出たとたんに、黄巾賊の一隊は早くも見つけてしまったのである。
「河まで行けば。県軍のいる河まで行けば!……」
遠くに帯のように流れが見えてきた。
しめたと、劉備は勇気をもり返したが、河畔まで来てもそこには何物の影もなかった。
宵に屯していたという県軍も、賊の勢力に怖れをなしたか、陣を払って何処かへ去ってしまったらしいのである。
李朱氾をはじめとして、騎馬の小方たち七、八騎はたちまち追いついて、
「止れッ」
「射るぞ」と、どなった。
鉄弓の弦をはなれた一矢は、白馬の環囲に突きささった。
喉に矢を立てた白馬は、棹立ちに躍り上がって、一声いななくと、どうと横ざまに仆れた。
芙蓉の身も、劉備の体も、共に大地へほうり捨てられていた。
驢を跳びおりた賊は、鉄弓を捨てて大剣を抜くもあり、槍を舞わして、劉備へいきなり突っかけてくるもあった。
(2023.11.2)
二
「もうこれまで」
劉備もついに観念した。避けようもない賊の包囲だ。斬り死せんものと覚悟をきめた。
劉備は、賊に飛びついて、槍を奪い、そして大音に、
「四民を悩ます害虫ども、もはや免しはおかぬ。 県の劉備玄徳が腕のほどを見よや」
県の劉備玄徳が腕のほどを見よや」
といって、捨身になった。
必死になって、七人の賊を相手に、ややしばらくは、一命をささえていたが、そのうちに、槍を打落され、よろめいて倒れたところを、李朱氾に馬のりに組み敷かれて、李の大剣は、ついに、彼の胸いたに突きつけられた。
「――おおういっ。待ってくれい」
呼ばわる声が近づいてくる。
「やっ、張卒じゃないか」
「そうだ。近頃、卒の中に入った下ッ端の張飛だ」
「小方、小方。殺してはいけません。その人間は、わしに渡して下さい」
「何? ……誰の命令で貴様はそんなことをいうのか」
「卒の張飛の命令です」
「ばかっ。張飛は、貴様自身じゃないか。卒の分際で」
と、いう言葉も終らぬ間に、そう罵っていた李朱氾の体は、二丈もうえの空へ飛んで行った。
(2023.11.10)
三
卒の張飛が、いきなり李朱氾をつまみ上げて、宙へ投げ飛ばした。
張飛は、さながら岩壁のような胸いたをそらして、
「むだな生命を捨てるより、おとなしく逃げ帰って、鴻家の姫と劉備の身は、先頃、県城を焼かれて鴻家の亡びた時、降参と偽って、黄巾賊の卒にはいっていた張飛という者の手に渡しましたと、報告しておけ」
「あっ! ……では汝は、鴻家の旧臣だな」
「いま気がついたか。此方は県城の南門衛少督を勤めていた鴻家の武士で名は張飛、字は翼徳と申すものだが無念や此方が他県へ公用で留守の間に、黄巾賊の輩のために、県城は焼かれ、主君は殺され、領民は苦しめられ、一夜に城地は焦土と化してしまった。――その無念さ、いかにもして怨みをはらしてくれんものと、身を偽り、敗走の兵と化けて、一時、其方どもの賊の中に、卒となって隠れていたのだ。――大方馬元義にも、また、総大将の兇賊張角にも、よく申しておけ。いずれいつかはきっと、張飛翼徳が思い知らせてくるるぞと」
劉備は、茫然と、張飛の働きをながめていた。燕飛龍 、蹴れば雲を生じ、吠ゆれば風が起るようだった。
、蹴れば雲を生じ、吠ゆれば風が起るようだった。
「なんという豪傑だろう?」
「いや旅の人。えらい目に遭いましたなあ」
張飛は何事もなかったような顔して話しかけた。そして直ぐ、腰に帯びていた二剣のうちの一つをはずし、また、懐中から見おぼえのある茶の小壺を取出して、
「これはあなたの物でしょう。賊に奪り上げられたあなたの剣と茶壺です。さあ取っておきなさい」と、劉の手へ渡した。
(2023.11.13)
四
劉備は、剣と茶壺を、張飛の手から受取ると、幾度も感謝をあらわして、
「救っていただいた上に、この大事な二品まで、自分の手に戻るとは、なんだか、夢のような心地がします。ご恩は生涯忘れません」
と、いった。
張飛は、
「貴公がそれがしの旧主、鴻家の姫を助けだしてくれた義心に対して、自分も義をもってお答え申したのみです。
ちょうど、古塔のあたりから白馬にのって逃げた者があると、哨兵の知らせに、こよい黄巾賊の将兵が泊っていたかの寺が、すわと一度に、混雑におちた隙をうかがい、夕刻見ておいた貴公のその二品を、馬元義と李朱氾の眠っていた内陣の壇からすばやく奪い返し、追手の卒と共にこれまで馳けてきたものでござる。貴公の孝心と、誠実を天もよみし賜うて、自然お手に戻ったものでしょう」
と、理由をはなした。
張飛が武勇に誇らない謙遜なことばに、劉備はいよいよ感じて、感銘のあまり二品のうちの剣のほうを差しだして、
「これはお礼として、あなたに差上げましょう。茶は、故郷に待っている母の土産なので、頒つことはできませんが、剣は、あなたのような義胆の豪傑に持っていただけば、むしろ剣そのものも本望でしょうから」と、再び、張飛の手へ授けて云った。
張飛は、名剣を身に佩き、芙蓉の身を抱いて、白馬の上に移り、名残り惜しげに、
「いつかまた、再会の日もありましょうが、ではご機嫌よく」
「おお、きっとまた、会う日を待とう。あなたも武運めでたく、鴻家の再興を成しとげらるるように」
「ありがとう。では」
「おさらば――」
劉備の驢と、芙蓉を抱えた張飛の白馬とは、相顧りみながら、西と東に別れ去った。
(2023.11.16)
著者プロフィール
吉川 英治(よしかわ えいじ)
1892年 神奈川県生まれ。本名は吉川英次。小説家
1953年 菊池寛賞
1960年 文化勲章
1962年 毎日芸術賞
1962年 勲一等瑞宝賞 没時叙勲
他の作品
「宮本武蔵」
「新書太閤記」
「新・平家物語」など
※wikipediaより引用